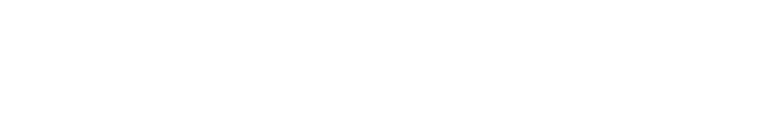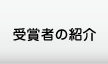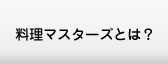|
|
||||||
| 司会: 高橋事務局長 | |||||||
その1)プロローグ: 地場イタリアンの立役者たち
高橋)
このトークショーのテーマを考えていたところ、奥田さんの名刺の「地場イタリアン」という文字が目に留まりました。そうだ、奥田さんと宮本さんの取り組みの共通点は'地場イタリアンとしての活動'だと思い至りまして「地場イタリアンで地域おこし」と設定してみました。
料理マスターズは、生産者さんたちと協働で取り組む料理人さんの顕彰制度です。今日も、料理人さんからお声をかけていただいてお二人の生産者さんにお越しいただいています。さっそく奥田さんからご紹介します。
奥田)
山形県の海側、庄内地方からやってまいりました。イタリアンレストランをやっている奥田と申します。
高橋)
奥田さん、生産者の坪池さんのご紹介をお願いします。
奥田)
アル・ケッチァーノがまだ有名ではない頃からお付き合いいただいて、一緒に「食の都」を作りましょうと同志になっていただきました。庄内が食の都になり、鶴岡市をユネスコの食文化都市として申請するにあたり、非常に力になっていただいている植酸農法の推進リーダーの坪池兵一(つぼいけ ひょういち)さんです。
高橋)
坪池さん、植酸農法のご紹介もあわせて自己紹介をお願いします。
坪池)
酒田から飛行機で来ました。なかなか勝手がわからず、羽田からのリムジンバスも非常に時間がかかり、やっとの思いでたどり着きました(笑)。
紹介いただいた植酸農法について説明させていただきます。植酸農法とは、これまで化学肥料など様々な要因で土地が悪化してしまった箇所を、有機酸で溶かし込み、除去していく、消し去ってしまう農法です。
皆さんは『連作障害』という言葉を聞いたことがありますか。連作障害はなぜ起きるか、ということです。生産者が欲を出すからです。化学肥料や農薬を使いながら、出荷量を多くするために連作するのです。こうして薬品を撒きつづけると土壌そのものが悪化してきます。
そこで植酸農法の考えでは、悪化した部分を洗濯しようとするのです。服が汚れたら、服を洗うでしょう?服がきれいになるまで洗濯機でぐるぐる回す―そういう行動を、有機酸を使って土壌に対してやっていくのです。そうすると有害物質など毒性のある物質が土壌から消えていきます。有害物質の排除によって美味しい野菜ができる、根っこからいい養分を吸い上げて良い野菜が育っていくんだと理解いただければ幸いです。簡単に説明するとこういうことです。
高橋)
続いて宮本さん、自己紹介からお願いします。
宮本)
熊本からやってきました宮本です。熊本市内でイタリア料理店をしております。こちらの井(い)さんは、私にいつもあか牛を提供してくださる方で、阿蘇の草原を守りたいという想いを一つにして頑張っておられる生産者のお一人です。僕らは今、阿蘇を「世界農業遺産」に認定してもらおうと動いていまして、井さんにもいろいろと相談をさせていただいています。
井)
阿蘇の産山村(うぶやまむら)というところから来ました。ちょうど大分県境に、九州で一番高い九重山(くじゅうさん)という山があります。その山の麓です。九州は暖かいイメージがありますが、すごく寒いところです。去年はマイナス10度にもなりました。そういうところの牧場で牛を飼っています。水がきれいですので無農薬のコメも作っております。井信行(い のぶゆき)といいます。よろしくお願いします。
次号につづく
→ これまでの掲載分はこちら

----------------------------------------
その2)料理人と'とんがった生産者'の出会い -奥田シェフと坪池さん
高橋)
坪池さん、井さんお二人の自己紹介からもお分かりいただけますが、お二人はある意味で'とんがった生産者さん'、農法や環境にこだわりを持ち続けて追及されている生産者さんなんですね。そういう生産者さんと料理人がどういうきっかけで知り合ったのか、経緯を奥田さんからお願いします。
奥田)
アル・ケッチァーノがオープンしたのは2000年ですが、当時、不思議なことがありまして。地元で野菜が育っているのに、スーパーへ行くとよその県産の野菜が売られている。地元の人が地元の物を使えないという、不思議な、流通も絡んだ事情がありました。地元の風土で育った地元の野菜を使って自分のイタリアンを作る、という気持ちが私にはありましたので、生産者さんのところへ行って「野菜を売ってください」と言いました。すると売ってくれなかったんです。当時は農協が強かったからです。
そこで物々交換で幸せの交換を始めた。日本酒が好きだとわかったら日本酒をあげる、こっちは野菜をもらう。今日はトンカツを食べたいかなと思ったら豚肉を5切れ持って行く―そういう風に物々交換でやっていたら徐々に庄内から始まって日本中が変わって行った…そういう流れの突破口になった方です。
高橋)
たしかに奥田さんのところへ伺うと、あるいは奥田さんと一緒に行動していると、物々交換をしていますね。最初に手にしていたものと、最後に手に入れたものが全然変わっている。
奥田)
そうです。最後はトラック1台分になったりします。お金がかからないところなんです。そうやってきた、それでやれてきた所です。
高橋)
坪池さん、最初に奥田さんから物々交換の申し出があった時はいかがでした?
坪池)
そうですね。それまでは全て金銭でやりとりしていたところへ、エコマネーでやるというのですから、すごい方が来たなと思いました。「俺は売らないよ」と言ったのに欲しくてしょうがないんです。その上エコマネーで、と言いますから…。私は円が欲しいんですよ。でも円には縁がなかった感じで(笑)…それでエコマネーを使ってやりとりしてましたね。
奥田)
そうです、そうです。お金払ったことがないんです、いまだに…(笑)。はい、時々伝票がついてきますね。
坪池)
その代わりに私がお店に行った時にはただで食べてきます。
奥田)
息子さんの結婚式もうちでやっていただいたんです。
坪池)
はい。
奥田)
あの時は、坪池さんが泣かないから、玉ねぎを使って泣かせようとしました。
坪池)
私の挨拶のときに、奥田シェフが脇でごそごそやっているので見たら玉ねぎをすっていたんです。
奥田)
玉ねぎの辛さも坪池さんから教えてもらいましたから、恩返しです。そういう関係です。
高橋)
なるほど(笑)。
奥田)
坪池さんは植物のなりたちとか、「窒素・リン酸・カリ」*1とか教えてくれたんです。私はそんなに頭が良くなかったんですが、納得するまで繰り返し教えてくれまして。今、私はいろいろな料理雑誌で語っていますけど、全部受け売りです。
高橋)
でも奥田さんのすごいところは、他の地方で仕事があると、まず自治体がつくった博物館や記念館へ出かけて、その土地の特産物の研究結果を真面目に、社会科見学のようにしっかり勉強、吸収するんですよね。それを別の機会に喋っておられる。
奥田)
たとえば庄内でやるべき料理は庄内の気候風土と、庄内に流れている水に、人が入ってどういう歴史を重ねてきたかということで、庄内の料理になるんです。中国では海と接する地方が少ないとか、川の水が汚くて茹でられないから蒸すとか、なぜ油で揚げるかというような、本には書かれていない、本には書きにくい答えが全部、博物館のような所へ行くとわかります。なぜフランス料理が旨味を出して煮詰めていくのか、という答えはその土地の土と水、そして人の歴史が影響しています。
料理マスターズとして頼まれて地域興しの仕事でよその地方へ出かけた時は、空から山や田んぼ、土の色を見てから博物館へ行って、人がどういう歴史を作ったかを見るようにします。こういうことに気づかせてくれたのも坪池さんです。
高橋)
生産者の方々は自然と土に向かい合って、日々実験をされているので、知識を頭で理解しているだけではなくて体にしみ込んでいる、実際に生きる知識になっているので、本に書いていないことをたくさんご存知ですね。それを引き出すことができるのが、料理人の上手なところなんじゃないでしょうか。そうした知識を料理へ生かすということも含めて。
奥田)
そうです。昔の歌手みたいに歌っているだけじゃダメなんです。今は歌いながら踊れないと売れませんよね。それと同じで料理人も、料理しながら色んな方やものと交わっていかないと…これは高橋さんから教えてもらいました。
高橋)
いやいやとんでもない。
*1 窒素・リン酸・カリ: 肥料の三大要素ともいわれる窒素、リン酸、カリウムが不足した土壌では農業は持続不可能といわれている。
次号につづく
→ これまでの掲載分はこちら

----------------------------------------
その3)料理人と'とんがった生産者'の出会い −宮本シェフと井さん
高橋)
次は宮本さんと生産者さんとの出会いについて伺いたいです。初めて宮本さんのところへ取材に行った時に感動しましたが、つきあっておられる生産者さんが非常に独特で、個性があって素晴らしい方たちでした。「どうやって、こういう生産者さんたちを見つけたんですか」と宮本さんにお尋ねしましたね。
宮本)
僕がイタリアから帰ってきたのは約11年前です。何度かご一緒していましたが、奥田さんが生産者さんと交流を始めた理由を今日初めて聞きました。僕も同じで、八百屋さんに頼んだら玉ねぎは北海道産、ホウレン草やセロリは長野産が来て、地元のものが使えない。熊本は農業県なのになんで地元のものが使えないんだという疑問がヒントになって。
当時は「道の駅」がブームでしたが、地産地消という言葉はパソコンでまだ変換できない時代でした。道の駅を回って、おばちゃん、お母さんたちをつかまえて売っている野菜を全部買って帰りました。食べてみて自分が気に入った野菜を自分で使う様になっていった、というのがきっかけでした。帰国して4年くらいは他の店で働いていて、31歳で自分の店を始めたんです。たしか奥田さんもお店を始めたのは・・・。
奥田)
はい、私も31歳でした。
宮本)
僕が31の時、奥田さんがテレビの「情熱大陸」に出たのを見ました。
奥田)
常に目標とされています(笑)。
宮本)
そう、奥田さんが番組に出た時は36歳だったんですよね。僕は36の時に料理マスターズをもらいました。
奥田)
そうなんです。西の横綱目指しているんですよね(笑)。
宮本)
ははは・・・でもこうやって地元の野菜を採り入れていましたが、あくまで食材として見ていました。それがある時、家族が病気になって、普通の野菜を受け付けなくなった。食べられなくなった時に、仲間の生産者の野菜は食べられたんです。免疫が弱っていて食べられなくなっていた…この時、食べ物の本当の大事さに気づいて「ああ、こういう生産者さんたちが熊本にはいっぱいいる」「ただ食材を卸してもらう生産者さんと考えていたけれども、実はとても大事な人たちだった」ということを感じました。この人たちの野菜のおかげで、家族はすごく健康になりました。こういう人たちの農産物を地域の人たちに食べていただくためには、料理人が使わないといけない、と思い始めて今のような活動になっていきました。
すでに有名は生産者さんだった井さんとは、ずっと知り合いになりたいと思っていたんですが、あるきっかけがあってつながったんです。こういう草の根の活動をやっていると「類は友を呼ぶ」じゃないですけれど、だんだん不思議とそういう生産者さんが周りに集まってきて、会いに行くと、間を置かずに次の人と出会う機会があり、翌日にはその方の農場へ出かける、というようなことをやっていたら段々増えて。今では40軒くらいの農家さんと付き合えるようになりました。
高橋)
井さん、宮本さんから初めて連絡を受けた時、どんな感じを持たれましたか?
井)
そうですね、最初に電話をいただいて、まず、すごさを感じたのは'即'でしたね、行動が。電話で話しているうちに「明日、あるいはあさって(会いに行きます)」という感じだったので、非常に関心しました。
高橋)
実際に会われた時の印象はどうでした?
井)
えぇ、さらに輪をかけてすごい方だと思いました。農家は作るのは得意ですけど、買っていただく人がいるということはすごいことです。最初の話し合いが印象深いです。「農家」と「使っていただく方=シェフさん」の妥協点があると思うんですが、我々生産者は村で暮らしが立てばいいのです。それを一番理解していただいた。私の人生、出会いで支えられていますけど、宮本さんはその中でも天下一品でした。ちゃんと農家のことを考えておられる。価格設定もちゃんとしていただきました。
宮本)
価格を決めることをしたんです。僕らの場合は、このくらいでいいですよ、とおっしゃる価格に対してすべて100円とか200円をプラスして付けたんです。そうして使うと、喜んで作っていただけて。農家の人たちは皆さん良い人たちで「持ってきな」と言って、いっぱい持たせてくれるんですよ。そうすると儲かる部分がない。
僕らは無理言って作ってもらっている面もあります。だから井さんが「これは〇〇円でいいから」と言われたのを、生産者の方へリターンできるようなシステムを最初に整えました。牛の場合だと500キロくらいありますからキロ100円上げると結構な金額になりますけど。
井)
農家はまじめに物を作るというか、あまり計算しないというか、労働力をつぎ込んで物を育てることが好きな人が農家として残っていると思うんです。その人たちは自分だけじゃなく、農村集落や全体的なことを考えています。ただ、今の市場制では価格が安定しない。暮らせない。暮らせないから出ていく。出ていくことによって、過疎化して集落機能を存続できない村も出てきています。そういうところに「いや、この値段で買ってあげますよ」という動きが徐々に広がりつつありますけど、こうした動きが日本全国の効率の悪い農村集落に広がってくれれば、必ず農村は元気になりますし、それによって都会の人が憩える自然の場所も残っていく―そういう点からも宮本さんとのお付き合いは、今後にとってすごく明るい光ですね。今後ともよろしくお願いします。
次号につづく
→ これまでの掲載分はこちら

----------------------------------------
その4)地域おこし、生産者さんのやる気おこし
高橋)
チャレンジを続ける生産者の方々は年齢に関係なく目が輝いていますね。ほかの料理マスターズがお付き合いしている生産者さんにも感じますが、やる気があって新しいことに挑んでおられるので表情もエネルギーが漲っておられる…。
坪池)
やる気ということでは跡取り問題も関係しています。親父の背中を見て息子は育ちますが、嫁が来ないという理由で跡取りをしないという問題も出てきます。どうやったら、興味を持たせて跡を継がせることができるか。会社だったら社員を元気づけて存続させる方法を考えるのと同じで、農家も下手なことはできないです。
私の息子夫婦の場合は、最初の3年間は家から出しました。3年間、世間の荒波にもまれても、まともに生活できるようだったら帰ってきていいよと言ったんです。そしたら3年後にブーメランのように戻ってきました。戻ってきて「親父は二十歳で自分の家を建てたから、俺も。」と宣言して、自分の家を建てたんです。しかもオール電化の家です。そこで借金を抱えて、次に「親父、経営譲渡させてくれ」と言うんです。私は先日還暦を迎えまして、会社勤めなら定年ということで、経営から蚊帳の外になりました。今日もここへ来るときは手を振って送り出されました。
こういう状況は、安心半分で、怖さも半分あります。本当に経営をうまくやれるのかということです。これまで培ってきた財産として、土壌の良さだけは何とか確保しています。ただし、これ以上面積を広げると手がかかりすぎて、味を落とすことになると思います。今は息子が自分の力がどれだけあるかを試す期間でもあります。うまくやれなかったら親父がサポートすればいいんじゃないかなと思っています。
奥田)
うちでお付き合いしている生産者さんは全員、後継者がついたんです。
高橋)
生産者さん全員に跡継ぎがいるとは心強いですね。
奥田)
最後に残った羊の生産者さんも、先日、跡取りが見つかったので、もうすぐお祝いの会をします。
高橋)
井さんの方はいかがですか。跡取りは?
井)
そうですね、自然と跡取りになってくれましたね。農業しなさいとは1回も言わなかったんですが、農業大学を出まして。
高橋)
いいですね。親父の背中を見て育ってきたんですね。
宮本)
後継者は重要ですが、女性の存在も、農家さんにとっては非常に重要ですね。ご主人たちとは時々こうした機会で外で会えますが、奥さんはいつも置いてきぼりなので、僕たちは、奥さんたちを集めて「被害者の会」というのをやってます。僕と僕のお店の仲間と二人で、奥様をご招待して、食べて飲んで、カラオケで日々のうっぷんを晴らしていただいて、また日常に戻って旦那様を支えていただきます。 特に坪池さんや井さんのように外に向かっている生産者の旦那様を陰で支えるのは大変ですからね。
坪池)
今の宮本シェフのコメントにあやかって・・・女性がいないと農業は無理なんです。「百姓」という漢字を見てください。百の女が生きる、なんです。字のごとく、農家のかあちゃんが頑張らないと一方通行に走ってしまいます。
私は直売所もやっていますが、売れないものがあると、一度うちへ持ち帰っておかあちゃんが料理をして、翌日はその料理した物を売ります。そうすると、一次産業から脱皮して二次産業です。それを直売所で販売するので、三次産業もやっているんです。こうやっておかあちゃんが全部活気づけてくれるんです。女性がいないとだめです。だから私は未だにかあちゃんに頭があがらないです。
高橋)
井さんはいかがですか。
井)
農家は、家族労働ですね。企業的農業は今の段階では難しい。家族労働でやっていくという点から女性の力はすごいです。男は大雑把なんです。たとえば私は今日こうしてここに出てきています。もちろん家に長男はいますが。息子がもっと小さい頃を思い出すと、夫婦二人ともに外に出ていたら、農業の維持は難しいです。黙々と頑張っている人がいて初めて農家は成り立ちますので、女性の活躍、働きはすごく大切ですね。
高橋)
生産者の方も料理人の方も陰で支える女性にも気を配る、それが最終的には成功する道だったりするんでしょうね。料理人のお二人はどうですか。
奥田)
二の次になっていますね、自分の家族は。でもついて来てくれています。とても感謝しています。
宮本)
僕も店から帰るのが1時や2時で、翌朝の8時前には出かけます。休日は農家さんのところへ行っています。
井)
宮本さんの奥様は素晴らしい方で、支えておられます。私は宮本さんの健康を心配しています。話も上手だし、文章もいろいろ書いて知事や大学へ提出したりして、大活躍ですけど、いつ眠っているのかと心配しています。
奥田)
スローフードと言いながら、料理人は忙しい。原稿書くのはお店が閉まったあと、どうしても1時過ぎになりませんか。お客様が健康になるための知識を披露しながら、自分たちが一番不摂生だったりして。
宮本)
そうですね(笑)。
高橋)
料理人さんは地域や生産者さんなど、気にかけて盛り上げてくださってありがたいですが、医者の不養生と同様、料理人さんも健康には気を付けていただきたいですね。そして美味しいお料理を作ってください。皆さん、今日は素晴らしいトークをありがとうございました。
次号より「アランシャペルの門下生」(音羽和紀シェフ・西原金蔵シェフ)を掲載いたします。
→ これまでの掲載分はこちら

----------------------------------------