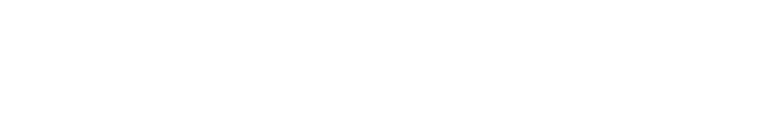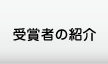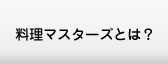|
|
||||||||||
「土の力、草の力、自然の力」
その1)虫の知恵、先人の知恵 <1>
土の料理人との出会い
高橋)
まず、料理人のお二人から、どういう思いで日々のお料理を作っておられるか、その辺の料理哲学のあたりを語って頂こうと思います。北沢さんからお願いします。
北沢)
えー、料理人がこんなこと言うと怒られますけど、料理する上で一番大事なことは何かということを考えまして、フォアグラやトリュフやキャビアが大事なのではないという事に気がついたんです。一番大事なのは、まず、お天道様の光、ね、陽光。それから、空気、それから水…この三つが、料理する上の最も大事ではないかと気がつきました。
というのは、何のために食べるか、何のために料理するかという事を考えてみると至って簡単で、人は元気で健康に生きていくために食べるのであって、そのために料理を作るのだということに思い至ったんです。だったらなるべく田舎の、土に近づいたところで、生産者の近くに寄り添ってみようと。
それで信州の山の中で店をはじめて21年になるんです。この21年の間に、村の生産者の人達とご縁がいっぱいできました。中でも今日来ていただいた「ゆい自然農園」の若い嫁さんの師匠であり義父である由井さんは、日本ではあまり知られていない頃に無農薬農業を始めた人です。由井さんたちとお付き合いしていると、土の恵み、そして土をちゃんと料理している。こういう農家の人たちは、やっぱり俺よりも料理人じゃないかと思います。
朝日新聞のコラムに「土の料理人」とか、「風土の料理人」とも書かせてもらっていますが、土を料理する生産者、農家の人達のほうが、よほど料理人ではないか、土が作り出す料理以上のものは俺は作れねえな、と最初から料理人放棄をして、「土の料理人」の人たちが作ってくれたもの、土の滋味や、土が恵んでくれるものを、食べてくれる人にストレートに伝えられたらと思っています。
地域の風土という大きいお皿の上にはすでにもうご馳走がいっぱい載っかってると思うんです…その風土という大きい皿にのっかってるものを、自分の店という小さい皿の上にいかに集積して出すか、という工夫…俺は、それが食べることの理に一番かなっているんじゃないかと考えて、こんなことを続けています。
高橋)
ありがとうございます。では続いて辺銀さんからもお願いします。
辺銀)
私の場合は今年で日本に来てちょうど25年、日本の生活が人生の半分を超えました。以前は中国で映画やカメラの仕事をやってまして、東京で勤めていた会社が倒産したのがきっかけで13年前に石垣島に移住しました。
それまで料理という仕事とは全く無縁でした。カミさんは浅草生まれの江戸っ子で、二人ともただの食いしん坊で、いろんなところに旅していろんなものを見つけては家で作って食べたり。15年前に南極に行った後に私が帰化して、辺銀という名前をつけました。日本では唯一の姓です。
沖縄に移住してからは、毎日市場で食べたもの、見たもの、感じたもの、それを自分の手で何とか再現して…昔から、ちっちゃな食堂をやるのが夢だったんですが、まさか石垣でできると思わなかったですね。
石垣では基本的に地産のもの、海の中のもの、その辺で生えてる虫も食べないものを採ってきてちょっとアレンジして、日々料理を作っております。基本的に島のおじい、おばあが作ったもの、庭で作ったものを分けていただいて使っております。あとは自分のちっちゃな庭で家庭菜園もやっております。無農薬よりは、その辺に生えている自然ものを採ってきて使うようにもしております。
高橋)
お二人とも、普段から自然と非常に近く接しておられますね。
次号につづく


その1)虫の知恵、先人の知恵 <2>
道端でムシャムシャ―「一木一草」を知る
高橋)
辺銀さんと一緒に農園に行かせてもらったことがありますが、行く途中の、その辺に生えている草もムシャムシャされてましたね(笑)。
辺銀)
うちの場合は野菜を自分達でつくったりするほかに、その辺に生えている雑草とか、島のおじい、おばあに教えてもらったものを勝手に採ってきて料理にしたり、そういう風にやっております。
沖縄は珊瑚でできている島なのでほとんどの土はアルカリ性です。アルカリ性は野菜は全く作れないんです。一部の土地を酸性に改良して野菜を作っていますけど、気候や季節にも左右されるので、そんなに沢山の野菜は作れないです。基本的に1月から4月くらいまでは、沖縄で野菜が採れる時季です。
高橋)
なるほど。その辺に生えている雑草が食材になるというのは面白いですね。そういえば、北沢さんも試食で「白人参」を出されていましたけど。ああいうものはどういうところで見つけられるですか?
北沢)
山です。普段、職人館にいるときはほとんど毎日山へ入っているんです。
でね、山へ行くと俺の料理の師匠は野の動物なんだね。辺銀さんも今、雑草という草はないって言ってたし、島にあるもので豚を育てる、これと全く同じなんです。野っ原はただ見てるとただの緑ですよ。だけどね、一木一草(いちぼくいっそう)、よく読み解くんですよ。山の中に二十何年いてね、野を読むことはいくらかできるようになりましたね。六十過ぎて、細かい字を見るのは面倒だから、本より野っ原を読んでたほうがいいんだね。
高橋)
'野っ原を読む'とは新鮮な響きですね。
北沢)
野っ原を読んでるとね、何の動物が食べたのか、何の昆虫が食べたのか知らないけど、皆かじってありますよ。その残りを俺がかじってみて、あぁそうか、今、この植物のこの部分、たとえば根っこを食べてあるのか、茎を食べてあるか、葉っぱか、花か、芽食べてあるか、と一木一草読むんです。そうすると野の動物や昆虫は、一番の食べごろにその部分を食べていますよ。
そのおこぼれを俺がかじって「あぁそうか、今頃はこの植物のこの部分を食うとこんな味がするのか」と、本当に「野が恵まう味」を食べる、動物の舌になって食べているんですよ、片っ端から。辺銀さんも、よく野っ原に行ってはかじっていると聞いたけど、そうすると人間が作る前の食べ物の植物の状態、その野の植物の原点の味をよく味わうことができますよね。人間が品種改良する前の味だね。
それで里に帰ってきて、まな美さんたちが作ってくれる野菜をかじってみるんですよ。畑へ行ってね、そのままかじらせてもらってるんです。山で食べる、野が恵んでくれる野の味、それからまな美さんたちが作る野菜の味、これを舌の中でよく味わってみると、ちゃんとしたいい野菜はどこか野の味に近い、野性味というのがありますよ。野性味とか野趣ね。
高橋)
そうすると、北沢さんの師匠は虫、辺銀さんの師匠はおじい、おばあということですね。
次号につづく


-----------------------------------------------
野の味を忘れない、ということ
北沢)
この間も詩人の谷川俊太郎さんとの対談で話してたんですけど、最近は言葉とか、食べるものの野性味がどんどん失われてきていますよ。ところがね、ちゃんと作った野菜には結構、野生の味があるんだね。何の表現でもそうだと思うけど、みんな'のっぺらぼう'ではつまらない。料理や味にもアクセントが必要なんだね。アクセントとは全部うまけりゃだめで、たとえば、ふきのとうの強烈な苦味がちょっとあって、そこにリンゴの甘みを食べると、両方がちゃんと引き立つ。いわゆる「うまい」だけじゃなくて、むしろ「まずい」と言われる強烈な苦味とかそういうアクセントがものすごく大事だと思うんだよね。そういう点で俺はなるべくアクセントのあるものを作ってもらいたいし、いい野菜にはちゃんとアクセントがあると思うんだね。
高橋)
なるほど。たしかに苦みは人間の基本的な五味の中に入っていますね。苦味をよりおいしく感じてもらうような、工夫はされるんですか。
北沢)
工夫も何もないんだね。料理人がこんなこと言うと、また怒られるけれど。うまいとか、まずいとか、二元論ではないと俺は思うんだね。これは人間が作った価値観なんだよね。本来、野が恵むものにはうまいもまずいもない。あるがままを食らうことが食の原点だと思うんです。'ふきのとう'はふきのとうのあるがままの味、蕪は蕪であるがまま、人参は人参、ね。
余談だけど皆さん、まな美さんが'蕪'を新規開拓中ですんで買ってください。ほかの会社の'株'みたいに暴落することはないから(笑)。ちゃんと身体にやさしいという見返りがあるカブですから、どうぞカブ買ってみてください。
話を戻すと、「ああそうか、蕪は本来こういう味だったのか」と食べる人が感じるために、どうやって本来の蕪の味を増幅して伝えられるかということが、生産者の人たちと一緒にやってる、山の中の料理人の仕事だと思っているんですよ。俺が作ったものとか、俺が作ったソースだとか、入る余地が段々なくなってくるんですけど、食べてくれる人に野に近いもので伝えられればなと、そんな風に思っています。俺自身がますます料理人を否定しちゃって、駄目なんですけど(笑)。
高橋)
そういう風に言われてどうでしょう、生産者としては。
由井)
'由井さんち'では「北さんが切ると野菜は美味しくなる」という話になってます。
北さんのお店で地元の人が集まるパーティがあるんですが、お伺いするとうちの野菜が本当に切ったままで出てくるんです。こっちとしてはすごいプレッシャーで、私は慌てて旦那をつかまえて「ちょっと、まんまで出てきちゃったよ、どうする?大丈夫?」って言うんです。するとうちの旦那はその皿を見ながら「北さんが切ったから、大丈夫だよ」って。
もちろん私たちが美味しい野菜を作ることは大前提ですが、農家が、野菜本来の味を食べる人全員に直接伝えるのはとても難しいことです。なので、蕪っておいしい、人参ってこんな味だよ、野菜って美味しいんだよと伝えてくれる、そしてうちの父のことを土の料理人と呼んでいろいろなところで紹介してくださるのは、農家にとって本当にありがたくて、育てていただいているなと感じます。
高橋)
今のお二人の話で、料理マスターズの料理人と生産者の関係を垣間見ていただけるかと思います。辺銀さん、石垣の雑草の続きを、もう少し詳しくうかがえますか?
辺銀)
石垣は北沢さんのところと全く反対で、漁師、海人(うみんちゅ)が多い島です。さきほども話したように赤土が少なく、他県と比べたらそれほど野菜はたくさん採れません。1月くらいから4月くらいまでが野菜の時季、そのあと少し海草の時季があって、7、8、9月はフルーツの時季、それ以降は採れるものが少ないです。
その中で雑草のようなものが結構ありまして、本来身体にとても良いもので、おじいたち、おばあたちが昔から食べて長生きをしています。ただ、今は沖縄の長寿のイメージは少し落ちています。たしか今年の5月15日は沖縄が本土に返還されてちょうど40周年年になりますが、戦前からアメリカの影響が少しずつあって、さきほど試食で出させて頂いた島の野菜とか草とかを、40代くらいより下の若い方はほとんど知らないです。それはちょっと悲しい、残念なことです。で、自分なりに少しできることとして、少しでも多くの島の若い方に、もう一回、昔食べていた健康な野菜や草を食べていただきたいと思い、レシピを考えたりしています。探せばいろんな面白い料理ができると思っています。
それから、野菜作りといえば、数年前から僕は海外に行っていろんな国の新しい野菜の種を持ってきて、農家の方に新しい島の野菜として作ってもらっています。一部の野菜はもう成功しています。去年はチシャ*という野菜作りに成功しました。正月によくおせち料理で使うチシャですが、中国の内陸部のほうでは、太くて大根みたいなチシャが採れますので、これを石垣島で2人の農家の方に実験で作ってもらい、今は楽しんで使っております。これからもそういった新しい野菜作り、食材作りをどんどんやっていこうと思っております。
次号につづく
*チシャ: チシャトウ(萵苣塔、千社唐とも書く)。
お節料理に使われる食材。別名は茎レタス。中国では、翡翠色の茎が縁起がよいとされる。

その2)けものの旬、野菜の旬 <1>
もろみの力
高橋)
さて、もろみ豚という珍しい名前の豚肉について伺おうと思います。辺銀さんの試食メニューは「石垣産もろみ豚のスーチキ(塩漬け)の島野菜添え」でした。川満さん、最初に'もろみ'とうかがった時、味噌か醤油を作る過程の'もろみ'かなと思ったのですが、どういうものか教えていただけますか。それから、もろみを使って豚を育てる発想はどこから出てきたか、軌道に乗せるまでにいろいろとご苦労もされたと思いますが、いかがでしょう。
川満)
「もろみって何ですか」と皆さんによく尋かれるんですけれども、なんでそういう名前をつけたかというと、沖縄は泡盛という酒を造りますが、酒ができた後に'もろみ液'というのが出ます。この液は大変優れたアミノ酸を含んでいて、非常に身体にも良い。それでこの液を私のところで餌に採りいれて、ずっと研究して、肉が美味しく食べられるように努力して、ようやく辺銀さんのおかげで日の目が見られたんです。
石垣島で豚を養う場合、今は配合飼料つまり穀物ですが、輸入した飼料を使います。ですが昔の石垣島には良い餌がなかったので、泡盛を蒸留したあとの泡盛液を豚にあげていました。泡盛のかすというか液が豚にとって非常に良い、肉の臭みがなくなるということを当時の人は知ってたんです。
その後、配合飼料が主流になりまして、もろみの技術は廃れていきました。私は「良い肉を作りたい」という想いがあって、配合飼料だけでは質の高い肉、脂はちょっと作りづらいなと思い、何度も何度も試行錯誤で、餌の設計というか、配合割合を変えました。そのうち、地元で採れるもの、サトウキビに目をつけたんです、昔のもろみ液の話を思い出して。すると、サトウキビの糖蜜は無機質に非常に富んでいる、ビタミンもまあまあ含んでいるとわかったので、これを飼料にうまく組み合わせて、何回も何回も餌を作り直して、ようやく納得できる域というか、今、手に入る食材ではここが最良ではないか、というレベルまで来ました。それで「もろみ豚」という名前で使ってもらっています。
辺銀さんと10年前に知り合って、使ってもらって本当に自信がもてました。農家が自信を持つと、生産に対する意欲や生産能力がものすごく変わります。今回こういうふうに生産者を表に出してもらったことも本当に感激で、ありがたく思っています。
高橋)
さきほど、もろみ豚を試食していただいたところ、「脂が非常に身体にやさしい」という感想がありました。これはもろみを使うことと何か関係があるのでしょうか。
川満)
もろみ豚に関しては、臭みの元は肉に吸着されるたんぱく質が主流です。今の配合飼料は、魚粉あるいは血粉、あるいは豚や牛のたんぱく質などを使っています。一方で、狂牛病などの問題もあって配合飼料には厳しい規制があって、設計は大変なようです。そこで私のところでは、動物性たんぱく質を使わないようにしています。代わりに米を使います。お米にもアミノ酸としてたんぱく質が溶けていますから、それを上手く利用しながら、餌の設計を変えて、臭み―いわゆる獣臭(けものしゅう)ですね―それを意識しながら豚作りをしています。女の人や子供、特に女の人にスムーズに食べてもらえる食材作りを、やっぱり島にあるものでやりたい、と。非常に強くそれを感じて今、やっています。
次号につづく
→ これまでの掲載分はこちら

----------------------------------------